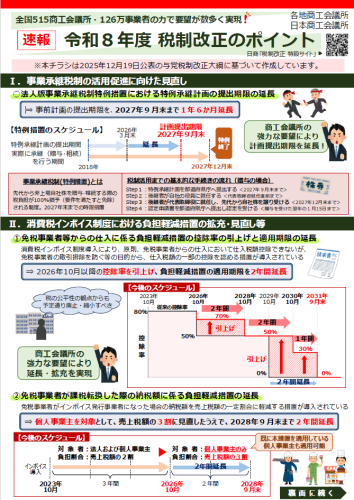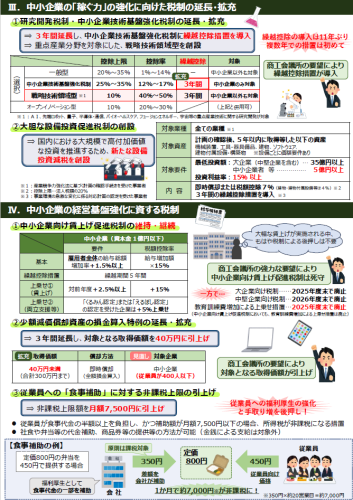お知らせ/ ブログ
おはようございます!
久しぶりの雨が降り、草木にはいい雨でしたね☔
しかしながら、雨が降るとうっとうしいので今朝はやんでホッとしています。
さて、マイナビキャリアリサーチLabより、
「2025年度 就職活動に対する保護者の意識調査」が公表されました。
就職活動を終えた、または活動中の学生を持つ保護者1,000名を対象とした調査です。
✨ 調査の主なポイント
📌 子どもに入社してほしい会社の特徴
🔹 「経営が安定している」が最多
🔹 「給与・賞与が良い」
🔹 「本人の希望に沿っている」
🔹 「社風が良い」
安定志向の強さがうかがえます。
📌 就職活動への意識
🔹 就活開始時期が早いことへの懸念
🔹 交通費やスーツ代などの費用負担への不安
保護者にとっても負担の大きいイベントであることが分かります。
📌 いわゆる「オヤカク」の実態
🔹 内定企業から保護者へ連絡があったケースは約46%
企業と保護者の接点も広がっています。
📌 キャリア教育・体験の影響
🔹 約半数の保護者が職業体験への参加を勧めたと回答
🔹 進路選択やキャリア形成への好影響を期待
一方で、体験機会の地域差・経済格差への懸念も示されています。
詳しくはこちら
🔗 <2025年度 就職活動に対する保護者の意識調査>
👉 マイナビキャリアリサーチLab 調査ページ
社労士のひとことコメント
今回の調査からは、
保護者の「安定志向」が改めて浮き彫りになりました。
🔹 経営の安定性
🔹 待遇の安心感
🔹 将来の見通し
企業にとっては、採用活動において
「学生本人」だけでなく「保護者の安心感」も重要な要素になっています。
テレワークや柔軟な働き方が広がる今、
地域を越えて人材を集められる時代です。
選ばれる企業になるためには、
保護者への安心感をどう示すかも鍵になりそうですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
2月ももう終わろうとしていますが、今日は国公立の2次試験の日です。
少子化の中、各大学が推薦枠を拡大しており、現役高校生は周りの友達が
次々に合格が決まっていく中で、あくまでも国公立を一般で受験する
お子さんの覚悟や精神力に心から敬意を表し、心の底から応援したいと思います。
頑張れ受験生!!
さて、日本商工会議所は、「令和8年度税制改正大綱」をもとに
中小企業向けの主な改正内容をまとめた動画を公表しました。
商工会議所の要望活動により、延長・拡充された制度も多く含まれています。
✨ 事業承継税制の見直し
📌 特例承継計画の提出期限を延長
🔹 提出期限を2027年9月末まで延長
🔹 実際の贈与・相続は2027年12月末まで
非上場株式の贈与・相続時に税負担が100%猶予される特例措置。
活用を検討している企業にとって重要な延長です。
✨ 消費税インボイス制度の負担軽減
📌 免税事業者等からの仕入れに係る負担軽減措置
🔹 控除率の引上げ
🔹 適用期限を2年間延長
📌 免税事業者が課税転換した場合
🔹 個人事業主は売上税額の3割負担へ見直し
🔹 2028年9月末まで延長
インボイス制度の影響緩和が図られています。
✨ 中小企業の「稼ぐ力」強化
📌 研究開発税制の延長・拡充
🔹 3年間延長
🔹 中小企業技術基盤強化税制に繰越控除導入
📌 大胆な設備投資促進税制の創設
🔹 即時償却または税額控除(最大7%)
🔹 3年間の繰越控除措置
国内投資を後押しする新制度です。
✨ 中小企業の経営基盤強化
📌 中小企業向け賃上げ促進税制は維持
🔹 給与増加率1.5%以上で税額控除
🔹 繰越控除5年間
🔹 くるみん・えるぼし認定で上乗せ
📌 少額減価償却資産の特例
🔹 取得価額40万円未満に引上げ
🔹 3年間延長
📌 食事補助の非課税上限引上げ
🔹 月額7,500円まで非課税
従業員の手取り増・福利厚生強化にもつながります。
詳しくはこちら
🔗 <中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」(PR動画)を公表>
👉 日本商工会議所ニュースページ
(3分弱の動画ですので、すぐに見られると思います)
👇の画像は、動画の最後にDLできるPDFです。
社労士のひとことコメント
今回の改正は、
🔹 事業承継
🔹 賃上げ
🔹 設備投資
🔹 福利厚生
など、中小企業経営に直結する内容が中心です。
税制は単なる「節税」ではなく、
経営戦略を後押しするツールでもあります。
現在、来年度の事業計画を策定したり、その発表会などが
開かれている会社も多いと思います。事業計画を立てる上でも
活用できそうですね。
それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!
おはようございます!
この週末はとても暖かく、2月とは思えない陽気でしたが
いかがお過ごしでしたか?
さて、厚生労働省・総務省が運営する
「テレワーク総合ポータルサイト」にて、
コラム18
📌 「テレワークで創出した時間の使い方」
が公開されました。
🌟 コラムのポイント
テレワークにより削減される代表的な時間は、
🔹 往復の通勤時間
🔹 移動・待機時間
コラムでは、その創出された時間を何に使っているのかを分析しています。
そして印象的なのが次の考え方です。
✨ テレワークは「戦略的投資」
🔹 個々人のパフォーマンスを最大化する仕組み
🔹 働き方の再定義につながる
🔹 結果として生産性向上へ
単なる「通勤がなくなる制度」ではなく、
働き方そのものを変える可能性があると示しています。
🌟 テレワークは採用戦略にも影響
テレワークを導入することで、
🔹 採用エリアの制限が小さくなる
🔹 全国から人材を募集できる
🔹 育児・介護など事情を抱える人材も活躍しやすい
働く場所に縛られない仕組みは、
企業の人材確保の可能性を大きく広げます。
詳しくはこちら
社労士のひとことコメント
テレワークは、単なる福利厚生ではありません。
🔹 生産性向上
🔹 人材確保
🔹 離職防止
に直結する「経営戦略」の一つです。
特に、人材不足が深刻化する中で、
採用エリアを全国に広げられる点は大きな強みになります。
“場所に縛られない会社”は、
人材から選ばれる会社へと近づきます。
制度を整えるだけでなく、
戦略としてどう活用するかがこれからのポイントですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね~✨昨日は、金曜日と思っていたらまさかの木曜日でした…💦
さて、日本年金機構では、
事業主や厚生年金保険の被保険者向けに、
📌 年金制度に関する情報
📌 手続き上の注意点
などをまとめた「日本年金機構からのお知らせ」を、原則毎月公表しています。
このたび、令和8年2月号(全国版)が公表されました。
💡 今月号の主な内容
<ご案内>
🔹 被扶養者の認定における年間収入の取扱い
👉この4月から取り扱いが変わります
🔹 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の考え方
📌注意事項
🔹 被保険者資格取得届の個人番号欄はよく確認して記入
📌お願い
🔹 外国籍従業員の厚生年金加入前後における国民年金手続き
どれも、日常実務に直結する内容ですね。
✨ 特に確認しておきたいポイント
<被扶養者認定の年間収入の考え方>
🔹 実際の収入だけでなく「労働契約内容」に基づく見込み収入がポイント
🔹 誤った認定は後日の取消や返還につながる可能性
📌 資格取得届の個人番号
🔹 記載誤りは手続き遅延の原因に
🔹 提出前のチェック体制を整えておくことが重要
✨詳しくはこちら
🔗 <「日本年金機構からのお知らせ」>
👉 令和8年2月号(全国版)PDF(日本年金機構)
✨ 社労士のひとことコメント
「日本年金機構からのお知らせ」は、
新しい改正や実務上の注意点がぎゅっと詰まっています。
🔹 被扶養者の認定
🔹 資格取得届の記載
🔹 外国籍従業員への対応
いずれも、後からトラブルになりやすい分野です。
毎月の情報をこまめに確認することが、
ミス防止と信頼維持につながりますね。
次の更新は24日(火)です。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊
最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。
みなさんは、いかがですか?
さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」
が公表されました。
あわせて、
💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」
も示されています。
🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方
特に注目されているのが、次のQ&Aです。
〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?
🔹 それぞれ別に端数処理するのか
🔹 合算してから端数処理するのか
回答では、
📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
📌 50銭超は切り上げて1円
と示されています。
🌟 実務上のポイント
🟡 標準報酬月額の場合
🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
🔹 端数処理の問題は基本的に生じない
🟡 標準賞与額の場合
🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
🔹 端数が生じる可能性あり
🌟 実務で気になる他のQ&A
〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
〇 給与明細に内訳の記載は必要?
🌟 支援金率はいくら?
- 国が一律の支援金率を示す仕組み
🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金
つまり、率は全国共通です。
🌟 給与明細への記載は義務?
🟡 法令上の義務はなし
🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
🔹 健康保険料に含めて徴収可能
ただし…
- 制度の趣旨を踏まえ
🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める
というスタンスが示されています。
🌟 実務担当者として考えたいこと
- 明細表示のあり方
🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
🔹 別項目として表示する方法
🔹 従業員への事前説明を行うこと
制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。
🌟 詳しくはこちら
🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
👉 通知本文(厚生労働省)
🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
👉 Q&A(厚生労働省)
支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。
🔹 明細に表示するかどうか
🔹 表示するならどう書くか
🔹 従業員にどう説明するか
制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。
単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋